クリニック開業時のオフラインでの集患対策
公開日:2023年02月21日 (火)更新日:2023年06月30日 (金)
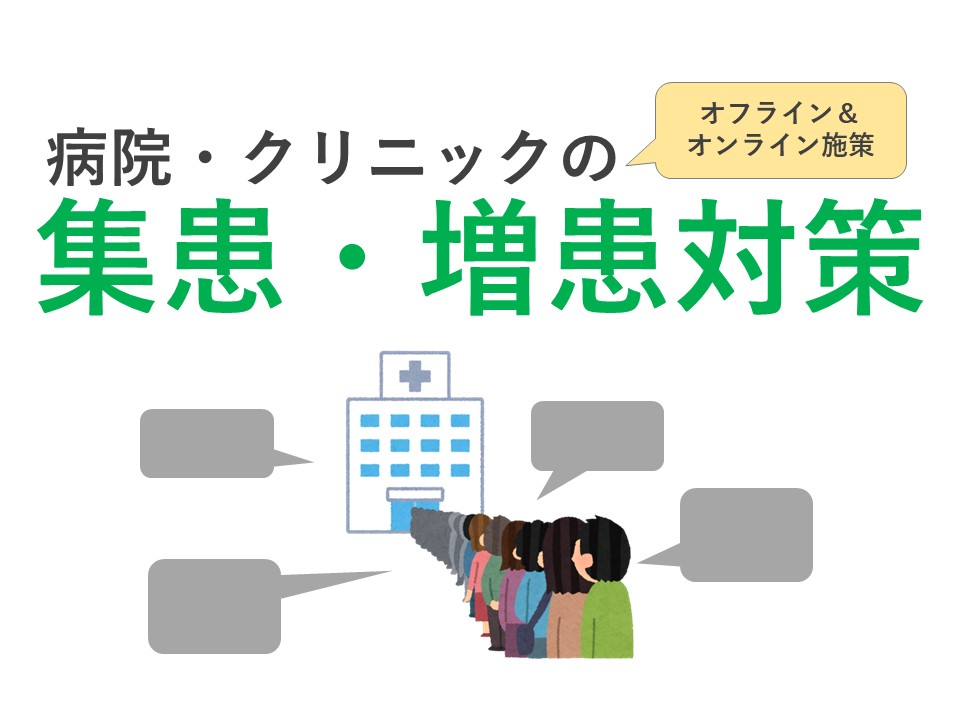
集患(しゅうかん)とは、カンタンに言うと患者を集めることです。集客とほぼ同義であり、転じてそのために打ち出す広告のことも指しています。そのほか患者を増やす増患も開業医は常に考えておかなければなりません。
そこで開業を目前に広告を検討されている先生から最近、患者が減ってしまいお悩みの先生までお役立ていただける、集患に関するオフライン広告の情報をまとめました。
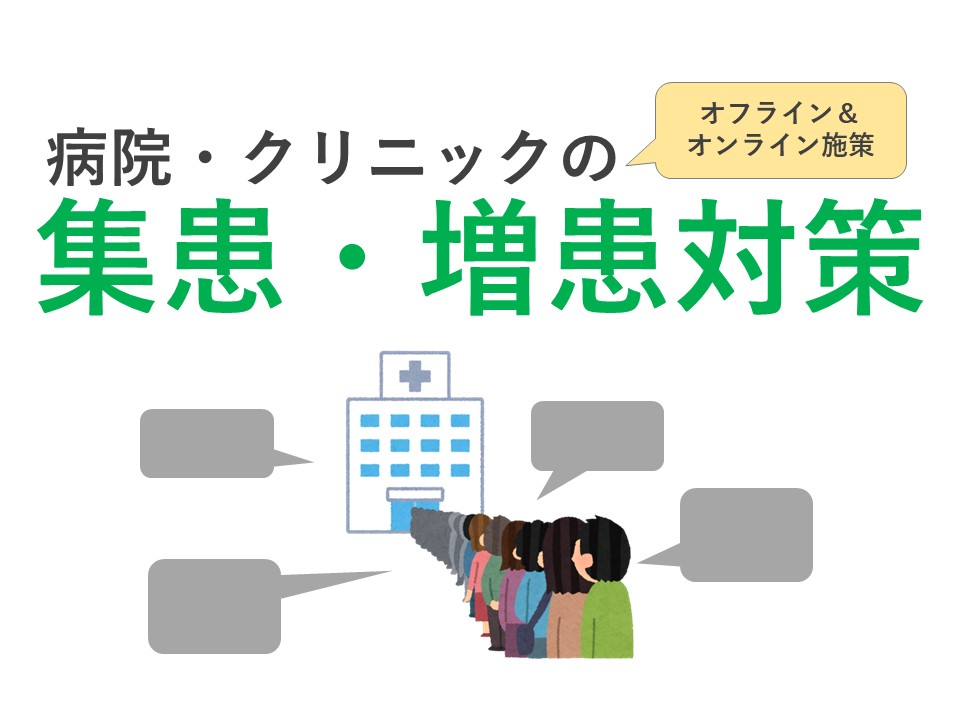
集患(しゅうかん)とは、カンタンに言うと患者を集めることです。集客とほぼ同義であり、転じてそのために打ち出す広告のことも指しています。そのほか患者を増やす増患も開業医は常に考えておかなければなりません。
そこで開業を目前に広告を検討されている先生から最近、患者が減ってしまいお悩みの先生までお役立ていただける、集患に関するオフライン広告の情報をまとめました。
目次
具体的には病気の診察・ケガの処置・治療・予防接種・健康診断などを必要としている方々を対象に、病院やクリニックの場所、診療科目、診察日、休診日などを知らせ、来院のきっかけをつくるために広告を打ち出すことです。
ホームページや駅看板広告などオンライン、オフラインに大きく分かれますが、さまざまな広告の種類があります。
病院やクリニックを新規開設する際、集患対策を行わない開業医はほぼいません。それだけ集患は大事なことです。しかも集患は開業医だけではなく、診察・治療を必要とする周辺の住民にとっても、とても有益なことです。
これまで近所に診てもらいたい科目のクリニックがなかった、遠方の病院にわざわざ通っていた、かかりつけ医と相性がわるく親切な医師がいてくれたらと思っていた人たちにとって、病院やクリニックの新規開設は朗報と言えます。
また集患をしていなかったら、そこに病院やクリニックがあることを知らないまま遠方に足を運んだり、不親切な対応をされてイヤな思いをされたりする患者を増やすことにつながるかもしれないのです。
そして開業医にとっては広告を出すことで初日から、患者さんが診療に訪れる可能性が高まり、いいスタートダッシュができますので、開業時の集患対策は必要です。ぜひ計画的に準備して積極的に広告を出していただきたいです。
まずはオンラインでの集患を見ていきます。
現在は、どこか体の調子がわるいときやケガをした際は応急処置方法をとりあえずインターネットで検索して調べるなど、オンラインを使って情報を得ようとします。
もちろんその情報の中に、診てくれる先生や近くのクリニックも含まれるため、オンライン広告を出しておくほうがいいです。
オンライン広告の種類はたくさんありますが、なかでも必要不可欠な広告は公式ホームページです。
ホームページはオンライン上の病院やクリニックの玄関・窓口といっても過言ではありません。
インターネットの特性上、匿名で「あること」「ないこと」書き込まれることも少なくありませんので、公式ホームページを用意して
・診療科目
・診察時間
・休診日
など正確な情報を出しておくべきです。ホームページには最低限、
医師/診療/設備/所在地/連絡先/公共交通機関
に関する情報を載せておくといいです。しかしホームページをポンと出すだけで集患につながるわけではありません。SEO対策、MEO対策が肝要です。
ご存知のとおり検索窓で「○○駅 クリニック」「○○が痛い 病院」などと検索すればユーザーに有益な情報が返ってきます。最上部に出てきたサイトはアクセスされやすく、一定数の集患につながっていると考えていいです。
それが開業場所に近い病院・クリニックなら間違いなく開設後は競合、ライバルになります。
ホームページを公開しても、なかなかアクセスが伸びない。そういうケースは少なくありません。検索サイトの雄であるGoogleなどは「ユーザーのことを第一に考えたコンテンツ」を簡単に見つけられる(検索上位に出す)ようにすると公表しています。
また「ユーザー第一のコンテンツ」の基準のひとつとして「実体験や深い知識を明確に示しているか」があり、多くの病院やクリニックのホームページには、医師としての臨床経験や医学知識をコラムなどにしたためて公開していたりします。
SEO対策を施すことで、ホームページにアクセスされる機会が増え、集患へとつながりやすくなります。
SEOの略がSearch Engine Optimizationであるのに対しMEOはMap Engine Optimizationで、地図検索最適化を指しています。
Googleで「クリニック」と検索した場合、最上部に3件のクリニックと地図が表示され、どこにクリニックがあるか教えてくれます。しかしこれは開業したからといって自動的に表示されるわけではなく、オーナー側が自分でGoogleビジネスプロフィールに自院の情報を登録しなければなりません。
最上部の検索結果に食い込むためには、登録内容を充実させ、ユーザーの口コミに丁寧に対応するなどの施策が有効とされています。
リスティング広告とは、わかりやすく言えばGoogle(YouTubeも含む)広告、Yahoo!広告を指し、検索と連動して表示される広告や、外部のウェブサイトやアプリにバナーやテキスト、動画で表示される広告もあります。
「○○駅前に開業」「○○市の○○専門医」などビジュアルや文字で訴えることで、集患できやすくなります。
SNSとはTwitter、Facebook、Instagram、LINEに代表されるソーシャル・ネットワーキング・サービスのことで、これらにも広告を流せます。極端な言い方をすると普段ほぼSNS経由でしか情報を見ない人たちも一定数いますので、そういうユーザーにもリーチできるよう、導線を用意しておく必要があります。
個人としてやらない主義の先生方も自院の集患のためにぜひ、取り組んでいただきたいのです。
医療現場でもヘルステックが浸透しておりパソコンやオンライン(インターネット)に明るい先生方もいらっしゃると思います。
ご自身でサーバーを契約して独学でホームページを作成したり、SEO、MEO対策をしたり、リスティング広告手配、SNSを運営したりすることは可能です。
しかし「餅は餅屋」で専門業者に依頼すると、よりクオリティが高いホームページや広告、より集患につながる結果を出してくれる可能性が高いです。そしてなによりも学会、診察と多忙な開業医にとっては、時間の節約になります。
ただし病院・クリニックは他業種とは違い、医療情報はGoogleがより厳しくサイトを審査するYMYLトピックに該当しています。また厚生労働省は医療法における病院等の広告規制(いわゆる医療広告ガイドライン)を設定しています。
したがって、それらに精通した業者選びが大前提です。
オフラインとはオンラインの対義語で、ここではインターネットに載るもの以外の広告を指します。パソコンやスマホ、インターネットが普及する前から活用されてきた歴史の長い広告で、現在も一定の効果があるから生き残っていると言い切れます。
この章では、駅看板をはじめとしたオフライン広告について見ていきます。
JR西日本によると1日平均の乗降人員が最も多いのは大阪駅の約58万人で、30位の宝塚駅でも44000人となっています(2021年度)。もちろん人口が少ないエリアになると数は減っていきますが、通勤・通学で利用する人が多い駅に看板を出すことで一定の効果を得られます。
掲示できる場所は限られていますが、改札前に掲示することで乗客だけではなく、駅ビルのショッピングモールなどに立ち寄った人たちにも見られ、ホームに掲示することで乗降客だけではなく停車中、電車にいる乗客らにも病院やクリニックの存在を知ってもらえます。
近隣住民の患者さんしか来ないだろうと思いがちですが、通勤・通学で定期を購入している方はもちろん途中下車が可能ですので、ホームの看板を見て来院されるケースも少なくありません。
今は電柱の数自体が減少傾向にありますが、電柱広告もまた地域に根差す病院やクリニックにとっては重要な広告媒体です。
電柱広告のフォーマットとしては最下部に現在地名を書くスタイルとなっていますので、地元の方だけではなく土地勘のない方にもリーチします。
駅前など人通りが多い場所に出せば集患につながり、病院周辺に出せば案内道標としても機能します。
バス停、車体(ラッピング)、バス車内のポスター広告や車内放送広告も病院やクリニックが多用している広告媒体です。
通勤・通学はもとより高齢者を中心にクルマを持っていない方の買い物・通院手段となっていることも多く、意外と見られています。
ただ駅看板、電柱広告、バス広告は埋まってしまっていれば、出したくても出せないのがデメリットで、早めに広告代理店などに問い合わせて掲載可能か、どのくらい待つか確認しておくといいです。
駅に設置され無料で読むことができる沿線情報誌、地域で発行されているフリーペーパー、コンビニなど店舗の出入り口に大量に置かれ無料配布されている冊子など地元の情報誌などは、地域密着の紙面構成でクリニックの周辺の読者に広告を届けることができます。
部数にもよりますが掲載枠が大きければ広告料は高く、小さくなるにつれて安くなります。またテキスト広告もありますが、読まれる方は本当に隅々まで目を通しますので、一定の集患を見込めます。
特に開業前、病院やクリニックから徒歩で通える圏内のご家庭やマンションに紙媒体で周知徹底することで、抜かりなく集患できます。
新聞はもちろんのこと前項でご紹介した地元の情報誌がポスティングされることがあり、そこにチラシを折り込んでもらうこともできます。
情報誌とは違い、チラシには枠という概念がないため、伝えたいことを自由に掲載でき、デザインも意のままにできるのが利点です。
そのほかオフラインでの集患対策については次章で取り上げるようなメリットがあります。
駅看板、電柱広告、バス広告、地元情報誌、チラシには以下3つの共通したメリットがあります。
オフライン広告は病院・クリニックの周辺に仕掛けることが多いためか、近隣に住む方や近隣の事業所に勤務している方が毎日のように、目にします。
そのため地域に根差して医療を展開しようとする開業医には、オフライン広告と親和性が高いと言えます。
パソコン、スマートフォンを持っていても十分に活用できていない方は一定数いて、WEB広告とは無縁です。
インターネット、SNS、アプリを活用している方の中にもウェブ広告を嫌い、広告動画が流れている間はスマホを置く、絶対に見ないようにしている方もいます。しつこいくらい頻繁に出てくる広告については、広告主に対し嫌悪感を持つ層すらいます。
そんな人たちにもすんなりと受け入れられているのが、オフライン広告なのです。
電話などで所在地を伝えるときに「○○の看板の前」と伝えると、地元の方ならすぐわかったりします。そのくらい駅看板、電柱広告などは私たちの潜在意識の中に刷り込まれていきます。
病院・クリニックの建物自体がオフライン広告の最たるものともいえますが、オンライン広告とは違い、風景、生活の一部となり受け入れられやすいのはオフラインの強みと言えます。
しかしながら、オフライン広告を出す際、気を付けていただきたいことがいくつかありますので、最終章でお伝えしていきます。
病院やクリニックの集患で駅看板などの広告を出す際、以下3つについて考慮する必要があります。
オンラインの項で解説したように、厚生労働省がいわゆる医療広告ガイドラインを設定しています。基本的なこととしては、
・他の病院やクリニックと比較して優良である旨の広告
・誇大広告
・公序良俗に反する内容の広告
はしないよう定められています。
駅看板、電柱広告、バス停の広告も屋外広告物に当たります。国土交通省によると屋外広告物法の目的には
・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止
があり、媒体元もそれらを考慮してデザイン審査を行います。たとえば閑静な住宅街で派手な配色の電柱広告は景観を損ねると言えますし、金色、銀色の素材で太陽光やカーライトに反射してしまうデザインは通行や視覚の妨げとなり危険度が高く審査には通らないでしょう。また、駅やバスの広告では鉄道会社やバス会社のデザイン審査も行われます。それぞれ独自の審査基準がありますので、広告代理店に相談するとよいでしょう。
オンラインなら最短数時間で出稿できたりしますが、オフライン広告はデザイン、看板の広告面や電柱広告のシートの印刷、設置など数週間~1、2カ月かかるケースもあります。
特に駅看板など、いい場所に空きがないと、半年後、1年後など待つ場合もありえます。そのため開業を決めたら真っ先に広告代理店に連絡し空き状況を確認し、先取りして押さえてしまうことをおすすめします。
いかがでしたでしょうか。今回は病院やクリニック開業医の集患についてご紹介しました。
病院やクリニックが集患を試みるとき、オンライン、オフラインともに広告が出せます。オンラインにはオンラインのよさ、オフラインにはオフラインのよさがあります。いずれにしても医療広告に精通した広告代理店や業者をつかまえて、早い段階から動かれることをおすすめします。
ekicoでは、交通広告を実施してみたいけどよくわからない、たくさん広告媒体があるけどどれを選べばいいんだろう、といった方に向けて、「交通広告・屋外広告選び方ガイドブック」を用意しております。
交通広告・屋外広告の選び方を種類から特徴、役割まで写真やイラストで分かりやすく解説しています。
ダウンロードはこちらから ⇒ 「交通広告・屋外広告選び方ガイドブック」
広告に興味があるけど何から始めたら良いかわからないといった質問から、広告の予算や時期、目的が決まっているので提案が欲しいといった具体的な問合せまで、気になることがあれば、問い合わせフォーム または電話(Tel 06-6621-1483)まで何でもご連絡ください!